脳神経疾患全般の臨床経験を積み、神経病理学の世界的権威のもとで研鑽を重ねる。幅広い知見を活かして福岡の地域医療を担う
はじめに、医師を志したきっかけを教えてください。
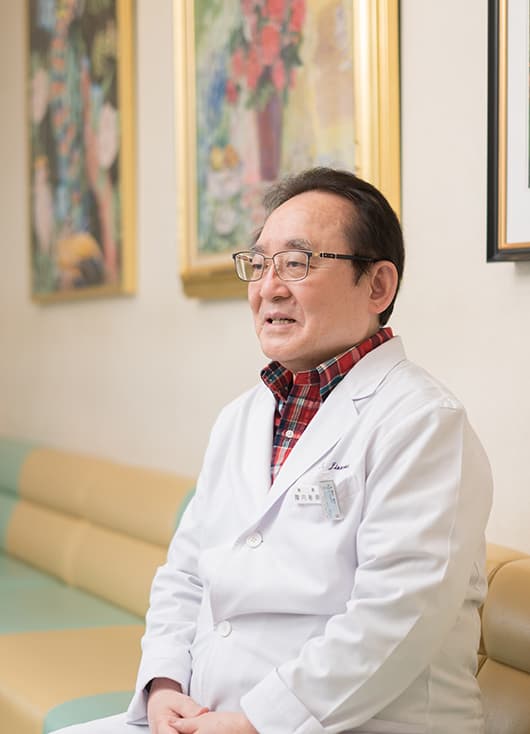
父が外科医として長崎で開業しており、診療所と自宅が同じ建物内にあったため、幼い頃から日常的に診療の現場に触れて育ちました。患者さん一人ひとりと真摯に向き合う父の姿を間近で見てきたことが、自然と「自分も医師になりたい」という想いにつながったのだと思います。
長崎大学医学部に進学され、脳神経外科を専攻されたそうですね。
大学在学中は、副業で『長崎大学管弦楽団』に所属し、チェロを担当していました。同じくチェロを弾いていた先輩にさまざまな相談をしていたのですが、進路の話になったとき、「脳神経外科は、医学の発展においてパイオニア的な役割を担っていて、とてもやりがいがある」と教えてくださったことが最初のきっかけになりました。その後、ほかの方の話を聞いたり、自分でも調べたりするなかで興味が深まり、脳神経外科に取り組みたいという気持ちが強くなり、長崎大学脳神経外科に入局しました。
勤務された国立長崎中央病院(現・国立病院機構長崎医療センター)や北九州市立八幡病院では、どのような症例に携わってこられたのでしょうか。
いずれの病院も、地域に根ざした中核的な医療機関として、多くの患者さんを受け入れており、軽症から重症まで幅広い症例を診療してきました。特に、医学博士論文のテーマを「脳卒中の病理」としていたこともあり、臨床でも脳梗塞・脳出血・くも膜下出血といった脳卒中症例に多く携わってきました。脳外科医として、脳梗塞や脳腫瘍、さらにはパーキンソン病に対する手術も数多く執刀し、貴重な経験を積ませていただきました。
その後、渡米され、モンテフィオーレメディカルセンターにも所属されたのですね。

モンテフィオーレメディカルセンターは、ニューヨーク市にある全米屈指の学術医療機関であり、アルバート・アインシュタイン医科大学の主要な教育病院として知られています。私はそこで、神経病理学・脳神経内科の分野における世界的権威である平野朝雄先生のもと、2年間にわたり研鑽を積む機会をいただきました。
平野先生は、神経変性疾患の研究において多大な功績を残され、細胞内に現れる特徴的な病理構造が「平野小体(Hirano bodies)」と名付けられていることでも広く知られています。92歳でご逝去されるまで数多くの研究者・臨床医を育てられ、世界の神経病理学の礎を築かれた方です。長崎大学時代にご指導いただいた教授が平野先生のご学友だったというご縁もあり、このような貴重な経験に恵まれました。国際的な医療現場で最先端の知見に触れ、脳神経外科医としての視野を大きく広げる、かけがえのない時間となりました。
帰国後は広島の公立みつぎ総合病院に勤務され、その後、福岡で開業されたとのことですが、その経緯をお聞かせください。
広島の公立みつぎ総合病院では、脳神経領域を中心に多くの症例に携わり、さらなる臨床経験を重ねることができました。
もともとは、いずれ長崎で開業していた父の病院を継ぐことも考えていたのですが、父が早くに亡くなったため、別の方に継承されました。開業を考えるにあたり、当時は広島で勤務していましたが、かつて勤務医として過ごした九州の地で、あらためて地域の方々に寄り添う医療を実践したいという思いが芽生え、1995年、福岡県春日市にて開業し、地域に根ざした診療を続けてまいりました。
