頭痛のスペシャリストとして、西日本各地からの患者に対応。MRIによる検査で脳疾患の早期発見・早期治療をサポート
現在、貴院にはどのような患者さんが来院されていますか?
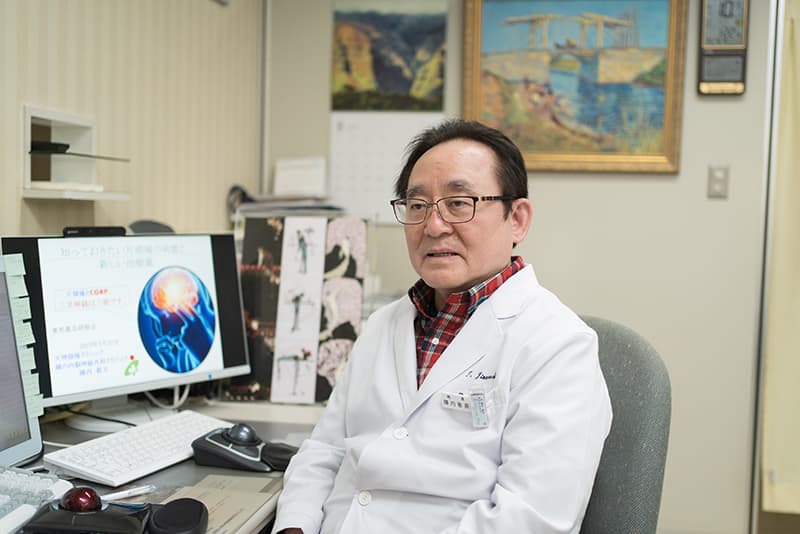
頭痛やめまい、しびれ、ふらつき、失神などの意識障害、頭をぶつけた、もの忘れなど、脳神経外科領域のさまざまな症状に対応していますので、来院される患者さんは、近隣の保育園に通う1~2歳のお子さんから20代〜50代の働き世代、不登校の学生、高齢者と幅広い年齢の方が受診されています。
主訴としては、頭痛が圧倒的に多く、めまいや手足のしびれを訴える方も少なくありません。ご高齢の方は「もの忘れ」が心配で受診されることが多いですね。なかでも、当院では片頭痛や群発頭痛の診療に力を入れており、これまでの治療実績が評価され、九州各地だけでなく、大阪をはじめとする関西方面から受診される方もいらっしゃいます。中には、東京に転勤後も遠隔診療で受診を継続中の患者さんもおられます。
群発頭痛は、かなり激しい痛みだとお聞きしたことがあります。
頭痛は大きく二つに分類されます。ひとつは、「一次性頭痛」と呼ばれるもので、明確な器質的疾患がなく、頭痛そのものが病気とされるタイプです。片頭痛や群発頭痛、緊張型頭痛などがこれにあたります。もうひとつは、「二次性頭痛」と呼ばれ、脳出血や脳腫瘍、感染症など、別の病気が原因となって起こる頭痛です。
このうち群発頭痛は、一次性頭痛の中でも特に激しい痛みを伴うことで知られています。多くは片側の目の奥に耐えがたい痛みが生じ、「自殺頭痛」と形容されるほど強烈です。発作は一定の周期で繰り返され、1回の発作は15分~3時間ほど続くことが一般的です。
また、特徴的なのは、発作が決まった時間帯、特に夜間から早朝にかけて起こりやすく、日中には痛みが嘘のように消えてしまうという点です。この「激しい痛みと無症状の繰り返し」も、群発頭痛の重要な診断の手がかりとなります。
頭痛の診療について、具体的にお聞かせいただけますか?
頭痛診療ではまず、患者さんから詳しくお話を伺うことから始めます。どのようなタイミングで起こるのか、痛みの性質や持続時間、伴う症状などを丁寧に伺い、必要に応じてMRIなどの画像検査を行って、脳の異常や重篤な疾患の有無を確認します。
片頭痛や群発頭痛といった一次性頭痛の治療では、「急性期治療(頓挫薬)」と「予防的治療」の両面からのアプローチが重要です。発作時の痛みを和らげる急性期治療としては、皮下注射や点鼻薬によるスマトリプタン製剤の使用、あるいは高濃度酸素吸入(100%酸素を毎分7〜10ℓで15分以上吸入)などが効果的とされています。これらは発作時に即効性のある治療手段として広く用いられています。
一方、発作の予防には、ベラパミルなどのカルシウム拮抗薬を中心とした薬物治療を行います。これにより、発作の頻度や強度を軽減できるケースが多く、継続的な服薬により症状が大幅に改善する患者さんも少なくありません。なかには、長期的に発作がみられなくなる、いわゆる「寛解」状態に入る方もいらっしゃいます。
また、薬物療法と並行して、生活習慣の見直しも重要な治療の一環です。規則正しい睡眠や栄養バランスのとれた食事、適度な運動、姿勢の改善、首や肩のストレッチなど、日常生活におけるセルフケアを積極的に取り入れることで、予防効果や治療効果を高めることができます。「自分自身も治療に参加して、自分が治療の主体である」ことを意識してもらう認知行動療法を実施すると、より良い治療成果につながるのです。
「めまい」に対する診療にも注力されているとお聞きしました。
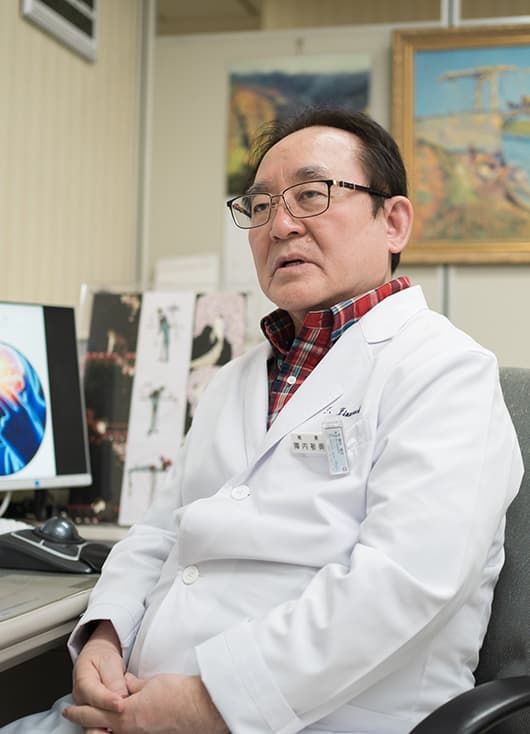
はい。頭痛と同様に、「めまい」の症状を訴えて来院される方も多くいらっしゃいます。実際、片頭痛の患者さんのうち約3分の2が、めまいの症状を併発しているともいわれています。
めまいの原因は多岐にわたり、耳の障害(良性発作性頭位めまい症、メニエール病など)をはじめ、貧血、低血圧、低血糖、脱水、ストレスといった身体的・心理的要因があげられます。さらに近年では、長時間スマートフォンをうつむいた姿勢で操作することにより、首まわりの血管や神経が圧迫され、頭痛やめまいを引き起こすケースも増加傾向にあります。当院では、こうした多様な原因に対応できるよう、精密な検査を行い、丁寧に診断することを心がけています。
また、生活習慣の見直しが症状の改善につながるケースも少なくありません。姿勢の改善や、首・肩まわりのストレッチなど、日常生活で無理なく取り入れられるセルフケアについても、具体的なアドバイスを行っています。
めまいの背後に脳梗塞や不整脈、大動脈解離など重大な疾患が隠れている可能性もあります。たとえ一時的な症状であっても、「たかがめまい」と軽視せず、早めに受診していただくことが大切です。
「物忘れ外来」も設けていらっしゃいますね。
物忘れの自覚は一般的に50代頃から増えてきますが、当院の「物忘れ外来」には、40代の女性など比較的若い世代の方も相談に来られます。
まずは、MRIによる脳の画像検査を実施し、脳萎縮の有無や血管性変化など、認知機能に影響を及ぼす異常がないかを評価します。若い方の場合、ストレスや疲労、睡眠不足といった生活要因による一時的な記憶障害であることも多く、診断には丁寧な問診や補助的な心理検査も欠かせません。万が一、アルツハイマー型認知症などが疑われる場合には、原因のひとつとされるアミロイドβタンパク(Aβ)の脳内蓄積に着目した治療法も検討します。近年は、アミロイドβに作用する疾患修飾薬(DMD)など、進行を遅らせる可能性のある薬剤も登場しており、治療選択肢が広がりつつあります。
精密な診断のために、MRIを導入されているのですね。

脳組織の萎縮や腫瘍の有無、脳血管のなどを調べるために欠かせないMRI検査では、閉所が苦手な方でも比較的楽な状態で検査を受けられ、高精細の画像が撮影できる新型1.5テスラMRI装置を導入して、的確な診断に活かしています。
さらに、2025年夏には新たに、乳がんの検査や全身のがん検査にも対応可能な高性能MRIの導入を予定しています。従来のマンモグラフィー検査は、圧迫による痛みや不快感が伴うことが課題とされていますが、MRIを活用することで、身体的な負担を軽減しながら精度の高い乳がん検査を行うことが可能になります。