循環器専門医として基幹病院で多様な心疾患の診療経験を積んだ後、地域医療を支える医院の2代目院長に就任
はじめに、多田先生が医師を志したきっかけと、循環器内科を専攻された理由をお聞かせください。
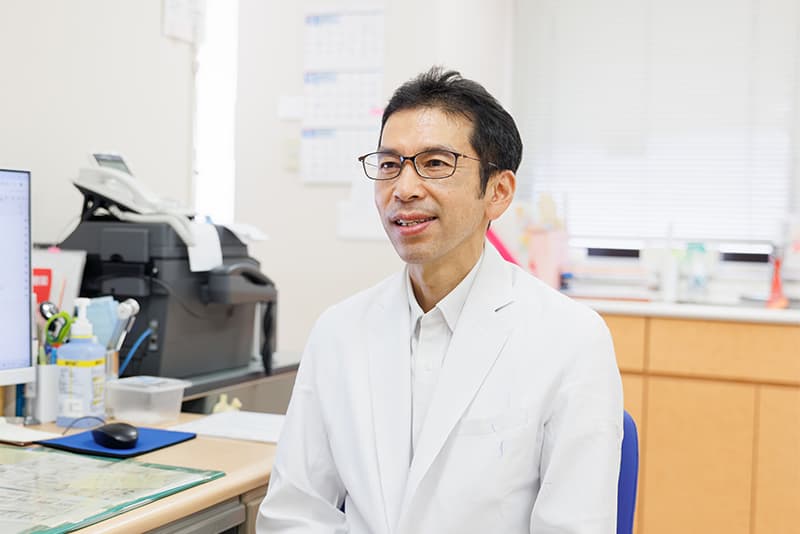
私の祖父は若い頃、医師を志して金沢医学専門学校(旧制金沢医科大学)に進学したものの、学業の途中で病気になり断念せざるを得なかったそうです。子どもの頃はその話をよく聞かされ、「将来は医師になれ」と刷り込まれたのもあってか(笑)、祖父に導かれるように自然と医師を目指すようになりました。
循環器内科を専門にしたのは、一言で言うと「サッカー部つながり」です。私が進学した岡山大学医学部のサッカー部は循環器内科の先輩が多く、話を聞いているうちに自分の性格にも合っているように感じて、卒業と同時に循環器内科に入局しました。循環器内科は内科的な治療が主体ですが、ときにはカテーテル治療など外科的な治療も行います。一刻を争う状況のなか、患者さんの命を救うために全力を尽くすところにも大きなやりがいを感じました。
入局後、内科でも研修を受けられていますね。
私が入局した頃は現在のような臨床研修制度はありませんでしたが、循環器内科の大江透教授(当時)が先進的な方で、全科にわたる幅広い研修を受けられるように全国の病院に送り出してくださったんです。私は、循環器にとどまらず全身を幅広く学びたいと考え、聖路加国際病院の内科で研修を受けました。
聖路加国際病院では、科目の垣根を越えた“ジェネラリスト”として、患者さんの全身を診るため内科診療の基礎を徹底的に教わりました。研修中には、故・日野原重明先生の回診に参加させていただく機会もあり、患者さんへの声かけやコミュニケーションのとり方などを間近で見て学びました。医師としての土台になる、貴重な経験を積むことができたと感じています。
貴院に入職されるまでのご経歴を教えてください。
倉敷中央病院循環器内科で後期研修を受けた後、尾道市民病院を経て、岡山大学の大学院に進みました。大学院では、ブルガダ症候群という心疾患と、透析患者の睡眠時無呼吸症候群に関する研究で博士号を取得。その後は、再び倉敷中央病院で心不全、心筋梗塞、狭心症、不整脈といった循環器疾患とともに、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の治療にも携わってきました。
約15年勤務した倉敷中央病院では、循環器の基礎知識からカテーテルの手技まで臨床現場で幅広く研鑽を積みました。特に、ICU(集中治療室)の責任者を長く務めていましたので、重度の心不全や心原性ショックの患者さんの救命、集中治療に多く携わりました。さまざまな症例と向き合い、内科も含めて多様な診療経験を積むことができました。
基幹病院で要職を務められていた先生が、貴院の院長に就任されたきっかけは何だったのでしょうか?
当院の草野功理事長がご高齢になり、後任を探されているということでお声がけいただいたのがきっかけです。じつは、理事長のご子息の草野研吾先生が循環器内科医で、大学のサッカー部の先輩というご縁もあります。
病院での勤務は忙しくもやりがいのある日々でしたが、ICU(集中治療室)は重症患者が中心で急性期対応に追われます。もっと患者さんと会話したり、治療後の管理や発症予防にも関われないかと考えていたときにお話をいただき、患者さんと長く付き合いながら診療していく「地域のかかりつけ医」に魅力を感じ、2025年4月から院長への就任をお受けしました。
当院の基本方針や診療内容に大きな変更はありませんが、これまでの内科と人工透析内科に加えて、私の専門の循環器内科と心臓リハビリテーション科を新設し幅広く診療しています。

