難易度の高い肝臓・胆嚢・膵臓領域の外科のエキスパートが、進行がんの早期発見や予防医療を実践する地域のかかりつけ医に転身
はじめに、熊谷先生が医師を志されたきっかけをお聞かせください。
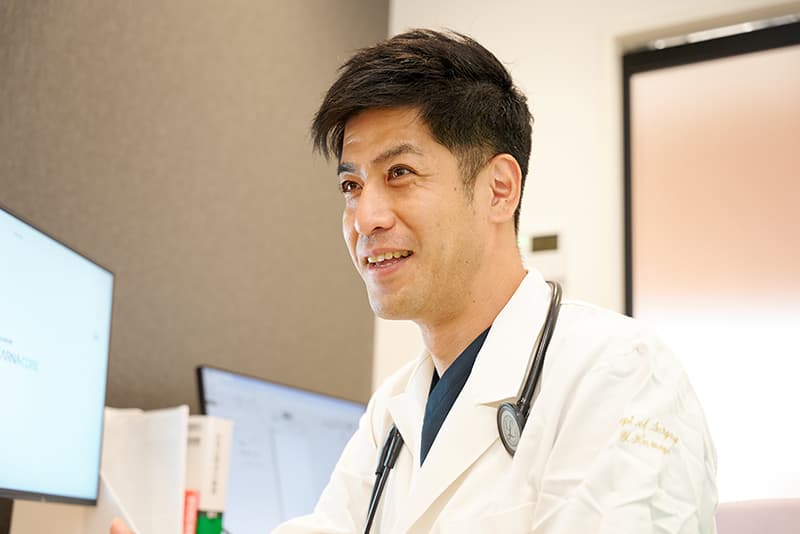
北海道には、いまもなお医療資源が限られている地域が少なくありません。私の祖父母も、羽幌町に住んでいた当時は、診察を受けるために旭川や札幌まで片道何時間もかけて通っていました。通院だけで丸一日がかりになることも多く、幼い頃からその大変さを目の当たりにしてきました。
その後、祖父が入院先で肺炎を患い、院内感染がきっかけで亡くなるという出来事もあり、身近な人を失った悔しさや無力感とともに、「自分にできることがあるはずだ」という思いが芽生え、医師の道を志す決意を固めました。
医学生になってからは、漫画やテレビドラマで知られる『Dr.コトー診療所』に出会い、離島の小さな診療所で地域医療に尽力するコトー先生の姿に深く心を動かされました。「いつか自分も、あんなふうに誰かの役に立てる医師になりたい」──そんな思いを胸に、今日まで歩んできました。
消化器外科を専攻されたのには、どのような理由があったのでしょうか?
将来的には、臓器や疾患を限定せず、全身を診られる医師になりたい──そんな思いがあり、当初は総合診療科への進路を考えていました。ただ同時に、一生をかけて追究できる専門分野も持ちたいという気持ちがあり、進路選びには少し迷いもありました。
そんな折、所属していた大学の野球部では、外科系に進む先輩が多く、体力勝負の厳しさや、その分だけ得られる達成感ややりがいについて、身近で聞く機会が多くありました。外科は、自分の手で治療に直接関わることができる分野。そこに大きな魅力を感じたのです。
なかでも消化器外科は、食道から胃腸、肝臓、膵臓まで、非常に多くの臓器を対象とし、幅広い疾患に対応できることが特徴です。全身を診たいという初志と、専門性を磨き続けたいという思い、その両方を叶えられるのがこの分野でした。
貴院を開業されるまでのご経歴を教えてください。
札幌医科大学を卒業後、東京臨海病院で初期臨床研修を修了し、消化器外科の技術をさらに高めるために、東京慈恵会医科大学附属病院の消化器外科に入局しました。在籍中は、消化器内視鏡の技術にも力を入れ、上部から下部まで幅広い消化器疾患の診療に携わってきました。
消化器外科医として6年目を迎えた頃からは、肝臓・胆嚢・膵臓といった肝胆膵領域に専門性を深めていきました。きっかけは、膵頭十二指腸切除術に助手として参加した際、その高度な手術技術に強く惹かれたことです。自分もこの分野でスキルを極めたいという思いが芽生え、肝胆膵外科に本格的に取り組むようになりました。
2014年には、東京慈恵会医科大学からの推薦を受け、がん研有明病院の肝胆膵外科に国内留学という形で派遣され、最先端の外科治療を学ぶ貴重な経験を積ませていただきました。このとき得た知見と技術は、現在の診療の大きな礎となっています。
がん研有明病院ではどのような診療に携わってこられたのでしょうか?
がん専門病院という特性上、携わる症例の多くは悪性腫瘍でした。肝胆膵を中心とした消化器がんの患者さんを対象に、開腹手術や腹腔鏡手術など数多くの手術に従事し、術後の全身管理まで一貫して担当。高い技術を持つ多くの優秀な医師たちとともに、日々、研鑽を重ねていました。また、当時すでに注目されていたロボット支援手術についても、知識と技術の習得に取り組み始めていました。
その後、東京近郊の関連病院で経験を積んでいた際、同郷の外科医の先生からお声がけいただきました。札幌市の時計台記念病院が新たに開設する「カレス記念病院」において、消化器外科の立ち上げに携わってほしいというご相談でした。ちょうど、地元・北海道に戻りたいという思いもあったタイミングで、自分にとっては非常にありがたいお話でした。
そして、カレス記念病院の消化器外科開設準備に一定のめどがついたのを機に、2025年7月、自身の理想とする医療をかたちにするべく、クリニックを開業するに至ります。
いずれは、生まれ育った北海道に戻るおつもりだったのですか?
はい。東京での勤務は、自分にとって“修行の場”という位置づけでした。北海道の地域医療に貢献したいという思いがずっとあり、そのために必要な専門医資格や学位の取得にも力を注いできました。そうした準備を重ねてきたからこそ、今回の開業でようやく念願が叶ったと感じています。
これからは、これまで高度医療機関で培ってきた診療技術を、地域の方々の病気の予防や早期発見に役立てていきたいと考えています。

