高度先進医療の現場で培った高い診療スキルを地域医療に還元。親子2代で呼吸器、アレルギー、循環器の専門診療が特長の内科医院を運営
はじめに、医師を志したきっかけをお聞かせください。
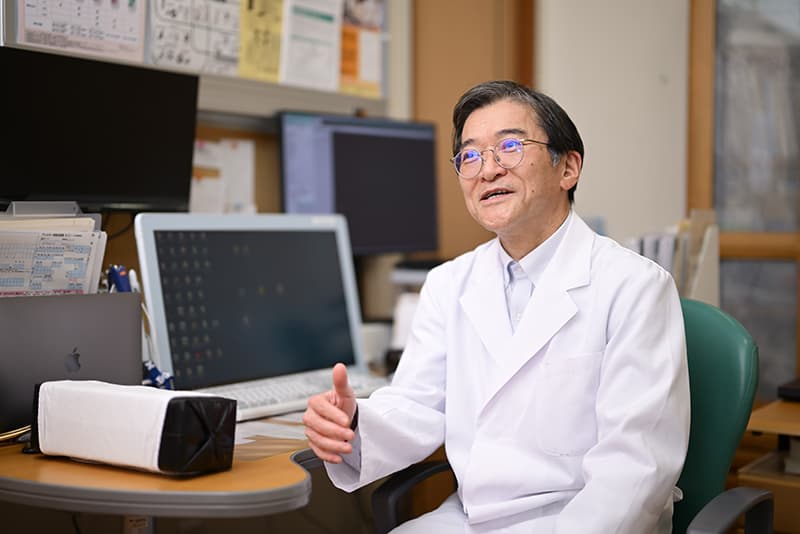
【中島院長】私の生まれ故郷の函館で父が内科の開業医をしていましたので、その影響が大きかったですね。真冬の厳しい寒さの中でも、患者さんに呼ばれると往診に駆けつけ、地域の人たちの健康を支えていました。成長にするにつれ、「医師は地域を支える仕事だ」という実感が高まり、やりがいを感じて、私も医師を目指すようになりました。
【佑樹副院長】私も幼い頃から、父のように医師になるのかなという思いを、心のどこかで抱いていました。そんな中、大学病院で働く父が多くの方々に頼りにされている姿を見て、「父のかっこよさ、医師のかっこよさ」を感じたことを覚えています。また、通っていた小児科の先生がとても優しく、子どもながらに「こんな先生になりたい」と憧れを持ったことも覚えています。そんなふうに、目指す医師像が身近にある環境で育つ中で、自然と医師の道に進みました。
開業医に転身されるまでのご経歴を教えてください。
【中島院長】帝京大学医学部を卒業後、同大学の附属病院に約15年勤務した後、都立広尾病院など地域の中核病院に勤務してきました。私は、呼吸器内科が専門ですので、勤務医時代は、肺炎や肺結核、気管支喘息、肺がんなどの検査から診断、治療まで幅広く携わっていました。中核病院では、呼吸器内科だけでなく、インフルエンザなど季節性の感染症や腹痛、花粉症といった内科全般も幅広く診療していましたので、その経験も現在の診療に活かせていると思っています。
中島院長は、特に気管支喘息について、専門性を追究されてきたそうですね。
【中島院長】気管支喘息の診療においては、「健康な人と変わらない日常生活の実現」を目指す治療方針を掲げる大田健先生のもとで学び、特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を合併するような難治性喘息の治療にも深く携わってきました。また、約1年半にわたりアメリカでも喘息の研究に従事し、最前線の知見と実践を積んできた経験があります。そこで得た知識や臨床スキルは、現在の診療にも大いに役立っており、患者さん一人ひとりに合わせたきめ細やかな治療につなげています。
佑樹先生は、現在は循環器内科を専門とされ、その前には、内科全般に幅広く携わってきたそうですね。
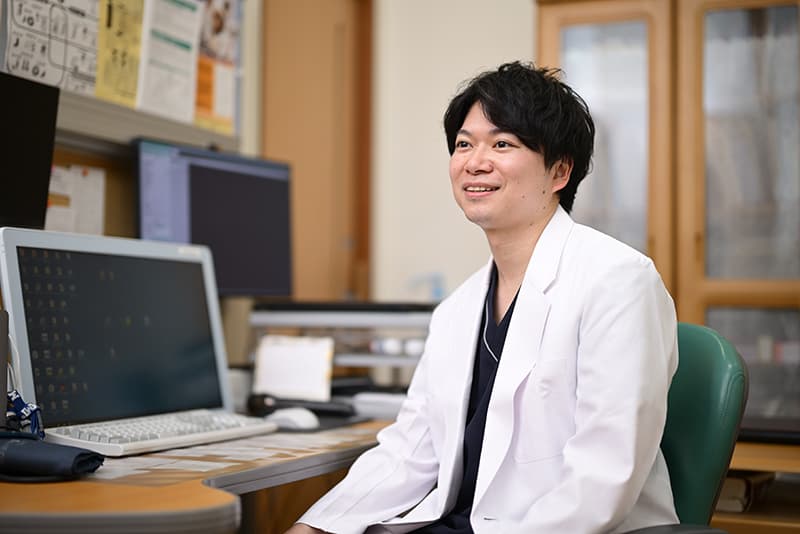
【佑樹副院長】私は、日本大学医学部を卒業し、国立病院機構災害医療センターと東京ベイ・浦安市川医療センターの総合内科での臨床研修後、日本大学医学部附属板橋病院の循環器内科に入局しました。
私が研修先に選んだ東京ベイ・浦安市川医療センターは、先進的かつ実践的な研修体制で知られる病院です。私は当初から、循環器疾患に特化するだけでなく、内科全般を広く診られる“ジェネラリスト”を志していました。東京ベイの総合内科では、ホスピタリストを育成しており、内科疾患(消化器疾患や呼吸器疾患、血液疾患、循環器疾患、生活習慣病といった多岐にわたる疾患含めて、全てが総合内科入院となり主体的に診療に診療に携わるため、患者さんの全身状態をトータルに診る力を養ってきました。
現在は循環器内科を専門としていますが、当時の経験は今でも診療の土台になっていると感じています。
研修後は、日大板橋病院で、狭心症や心筋梗塞のカテーテル治療、心臓弁膜症の診断に関わる心臓超音波検査(心エコー)を主として診療しています。ここ最近では心臓弁の治療で、僧帽弁閉鎖不全症を改善するマイトラクリップ治療など、心臓の専門診療について幅広く研鑽を重ねてきています。
高度先進医療に携わっていた中島院長が、開業を決断した理由は何だったのですか?
【中島院長】研究や高度先進医療も興味深かったのですが、私の父がそうだったように、地域の人たちにもっとも近い場所で、地域の人たちの健康を支えたいという気持ちが強くなり、2007年に開業しました。開業医は、医療の最初の入口を担っているだけに責任重大ですが、その分やりがいも感じています。
