風邪やインフルエンザ、生活習慣病から睡眠時無呼吸症候群まで幅広く診療。気管支喘息など呼吸器疾患では、検査から診断、治療まで専門診療を実施
現在は、どのような患者さんが多く来院されていますか?
当院は住宅街の中にあることもあり、患者さんの多くは近隣にお住まいの方です。開院から長い年月が経ち、地域の皆さんと一緒に年を重ねてきた実感がありますね。ご高齢の方が増えてきたのはもちろんのこと、開院当初に小さなお子さんだった方が、今では親となり、ご自身のお子さんを連れて受診されるなど、親子2代で通ってくださるケースもあります。
診療内容としては、風邪やインフルエンザ、コロナ感染症、腹痛、花粉症といった一般内科の症状から、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病、そして気管支喘息や肺炎といった呼吸器疾患まで、幅広い症状に対応しています。地域の「かかりつけ医」として、どんなお悩みにも気軽にご相談いただける存在でありたいと思っています。
呼吸器内科では、どのような専門的な診療が受けられるのでしょうか?
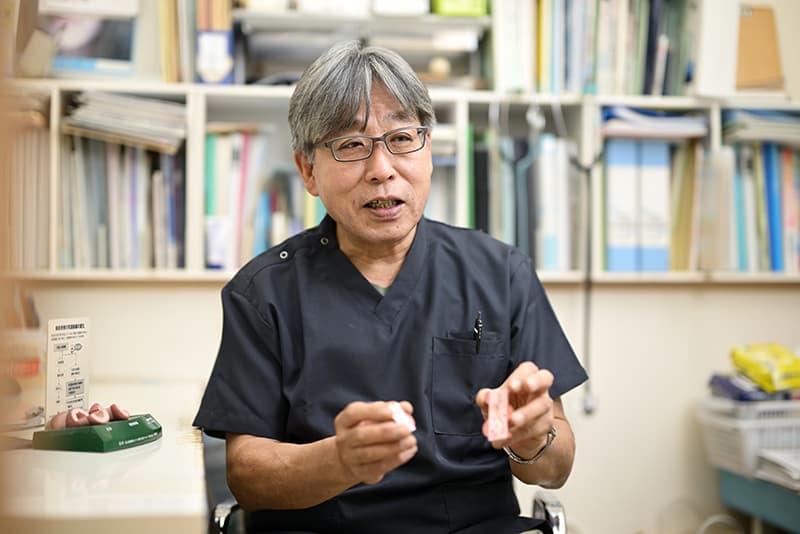
たとえば「咳がなかなか止まらない」といった場合、まずはいつ頃から、どのような咳が続いているのかといった経過を、問診で丁寧にお伺いします。そのうえで、血液検査でアレルギーの有無を確認し、レントゲン検査で肺炎や肺がんなどの可能性を除外します。さらに必要に応じて肺機能検査を行い、気管支喘息や咳喘息といった疾患の診断へとつなげていきます。
気管支喘息と診断された場合は、気管支拡張薬や吸入ステロイド薬などを用いた薬物療法を中心に、必要に応じて禁煙指導やアレルゲンの回避といった生活習慣の改善のアドバイスを行います。近年は治療薬の選択肢が広がり、クリニックでも十分に管理できる喘息が増えてきました。だからこそ、地域のかかりつけ医として、しっかりと対応していくことに力を入れています。
最近は、咳が長引いて困っている方が増えていると聞きます。
はい、実際に「咳が何週間も続いている」と訴えて来院される方が増えてきました。咳が長引く原因の中には、肺炎や肺がんなど重大な疾患が隠れていることもあるため、見落としのないよう慎重に診察・検査を行っています。
一方で、明らかな異常が見つからなかった場合でも、気管支拡張薬など、気管支喘息と同様の治療を行うことで改善するケースも少なくありません。いずれにしても、咳は体力を奪い、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。だからこそ、症状の背景にある原因を見極め、一人ひとりに寄り添った診療を大切にしています。
金澤先生が力を入れていらっしゃる、睡眠時無呼吸症候群の診療についても教えてください。
睡眠時無呼吸症候群は、かつては検査も治療も入院が必要なケースが一般的でしたが、現在は多くの場合、ご自宅で検査から治療まで行えるようになっています。日中に強い眠気がある、集中力が続かないといった症状があり、加えて肥満傾向や慢性的な鼻づまりがある方は、この病気のリスクが高いと考えられます。
当院では、まず簡易検査機器を貸し出し、ご自宅での睡眠状況を測定していただきます。その結果に応じて、必要であればCPAP(シーパップ)療法と呼ばれる持続陽圧呼吸療法を導入します。この治療は、眠っている間に気道が閉塞しないよう空気を送り続けることで、いびきや無呼吸を防ぎ、深い睡眠を保つことができます。
睡眠時無呼吸症候群は根本的な完治が難しい病態ではありますが、CPAPの導入によって睡眠の質が大きく改善し、日中の疲労感や集中力の低下といった症状の軽減が期待できます。重症度が高い場合や、心疾患などの合併症が疑われる場合には、専門の医療機関をご紹介しますので、どうぞ安心してご相談ください。
その他、貴院ではどのような診療を受けることができますか?
この地域でも高齢化が進んでおり、通院が難しくなってきた方も少なくありません。そうした患者さんには、往診による点滴療法や在宅酸素療法、疼痛のコントロールなど、必要に応じた在宅医療を行っています。
また、末期がんの患者さんに対するターミナルケアにも対応しており、できる限りご本人やご家族のご希望に沿ったかたちで、安心して過ごしていただけるよう努めています。