県内唯一のガンマナイフ治療医としても活躍した脳神経外科のエキスパートが、住民に永く慕われてきた脳神経外科クリニックを継承
はじめに、森先生が脳神経外科を志されたきっかけを教えてください。
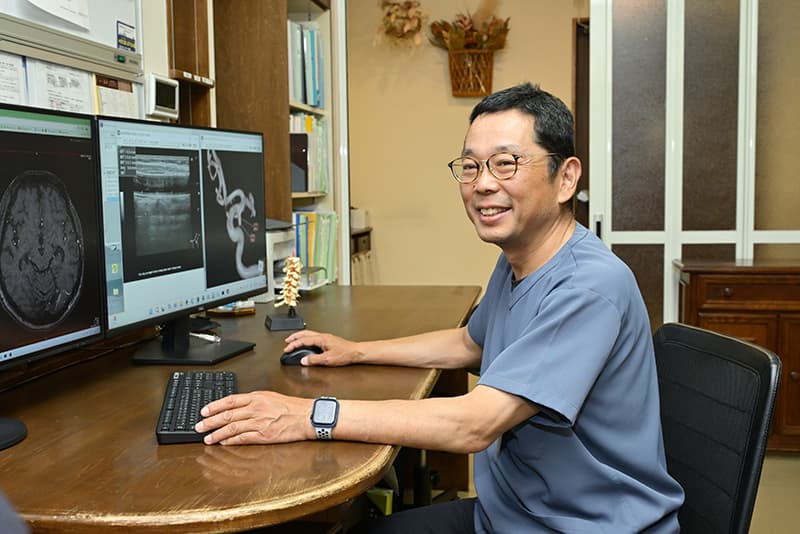
医学部時代、卒業前の臨床実習でさまざまな診療科を経験した中で、自らの手で直接患者さんを治療できる外科の分野に強く魅力を感じました。中でも脳神経外科は、人間の中枢である脳や神経を扱う非常に繊細かつ専門性の高い領域で、知れば知るほど奥深く、医師としてのやりがいを強く感じました。
脳神経外科といえば昼夜を問わず救急対応や処置、手術が当たり前の時代で当時は体力にもそれなりに自信がありましたので、「多少の激務にもきっと耐えられるだろう」と(笑)、迷わずこの道に進むことを決めました。
開業医に転身されるまでのご経歴についてお聞かせください。
長崎大学医学部を卒業後、同大学の脳神経外科に入局し、専門研修を含めて、長崎大学医学部附属病院、県立島原温泉病院、長崎労災病院、福岡記念病院などに勤務しました。いずれも急性期医療を担う地域の基幹病院・中核病院であり、脳卒中で救急搬送される患者さんの診療をはじめ、脳腫瘍、てんかん、頭部外傷など、幅広い脳神経疾患に対応する日々を通じて、臨床経験を深めてきました。
長崎労災病院では、当時国内有数の脳動脈瘤クリッピング術症例数を誇る横山博明先生のもとで、研修医として脳血管外科手術の技術と脳神経外科医としての哲学を間近で学ぶことができました。現在では考えられませんが当直明けでもそのまま急患の手術に入り、手術室で日付が替わることもざらでした。その後に赴任した福岡記念病院は これまた福岡でも当時救急車受け入れ台数1.2を争う救急病院で、脳卒中救急の最前線で昼夜問わず検査や手術に明け暮れていました。こうした最前線の現場での経験が、脳神経外科医としての診療の土台となり、今も大きな財産となっています。
福岡記念病院の「ガンマナイフセンター」立ち上げにも尽力されたそうですね。
はい。長崎大学医学部附属病院に戻った際には、のちの私の研究テーマとなる脳疾患に対する放射線治療に携わりました。臨床研究は「定位放射線治療」というテーマで中枢神経系の放射線治療分野での当時の最先端のテーマでした。折しも長崎大学脳神経外科は当時の柴田尚武教授が国内で初めて「直線加速器を用いた定位放射線治療」を立ち上げており、そのメンバーに加わる形で定位照射線治療の現場で患者さんの治療と基礎研究に打ち込むことができたのは非常に幸運であったと思います。
病棟医を経て脳神経外科専門医の資格を取得した後、福岡記念病院にガンマナイフ治療の専門センターを立ち上げるプロジェクトに参画し、その準備の一環として、ガンマナイフ治療の本拠地であるスウェーデンのカロリンスカ大学へ約2週間の短期留学と専門技術研修を受けました。3月のストックホルムは氷に包まれた美しくも凍てつく街でした。そこでガンマナイフの最新の知識と技術を習得し、帰国後は、1999年から福岡記念病院ガンマナイフセンターにてガンマナイフ治療を中心とした診療に従事しています。
ガンマナイフとは、どのような治療法なのでしょうか?

ガンマナイフ治療は、開頭手術を行わずに高精度のガンマ線(放射線)を病変部に集中照射し、腫瘍や血管奇形などの病巣を治療する放射線治療で低侵襲手術の先駆けといえる治療です。外科手術と比べて患者さんの身体的負担が少なく、入院期間も2泊3日と短縮できるのが特長です。今でこそ日本で30年の歴史を持つ確立された治療ですが当時は全く新しい治療で、他の医療機関から紹介されて来院される患者さんの多くは、不安な面持ちで診察室に入って来られました。そうした方々に安心して治療に臨んでいただけるよう、病気の概要から治療方法の選択肢まで、段階を追って丁寧に説明し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご理解・ご納得いただいたうえで治療を行うことを心がけてきました。
その後、ガンマナイフセンターの立ち上げに携わるため、長崎県諫早市の宮崎病院へ赴任し、脳卒中をはじめとする脳神経外科全般の診療と並行して、ガンマナイフ治療にも引き続き注力してきました。
これまでに、肺がんや乳がんなどからの脳転移をはじめ、聴神経鞘腫、髄膜腫、下垂体腺腫といった良性腫瘍、さらには脳動静脈奇形(AVM)や三叉神経痛など、延べ2,000例を超える患者さんの診断・治療・経過観察に一貫して関わってまいりました。
2022年に貴院の前身の「古賀脳神経外科」を継承されたそうですね。きっかけをお聞かせいただけますか?
宮崎病院にはおよそ約15年間勤務し、脳神経外科の一般診療とガンマナイフ治療の2足のわらじで診療に邁進してきました。このころは週4〜5日の午前外来診療に加えて、午後はガンマナイフ治療や脳外科手術を担当し、同時に救急対応や病棟管理、当直業務、休日の呼び出しにも対応するという目の回るように多忙な毎日でした。外来患者さんの数も非常に多く、私の外来診療の基盤は、まさに宮崎病院で築かれたものだと言っても過言ではありません。
当時の脳神経外科の実働部隊は、現在も親交のある同世代の医師が中心でした。長崎市の「サイノオ脳神経外科」院長・道祖尾伯史先生や、諫早市の「たにおか脳神経外科」院長・谷岡浩二先生とともに、様々な脳神経外科疾患に立ち向かい、当時の長崎県央~県南の脳神経外科診療の一翼を担っていたと思います。開業されたお二人は、私にとっても良き先輩であり、今でも多くの助言をいただいています。3人の関係は、さしずめ昔の野戦病院の“戦友”といったところでしょうか。
宮崎病院退職後は、愛野記念病院にて一人脳外科医として勤務するかたわら、ご縁をいただき長崎県のガンマナイフ患者さんを福岡記念病院で、沖縄県のガンマナイフ患者さんを那覇にある沖縄セントラル病院にて出張でのガンマナイフ治療を継続して行っていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、遠方への移動が難しくなり、出張による診療の継続も現実的に厳しくなってきたというのが実情でした。
そうした折に、「古賀脳神経外科」の古賀博明先生からお電話をいただいたのです。長崎大学脳神経外科の同門である先生が、古希を迎えるにあたりリタイアを検討されており、後継者として私に継承を打診してくださったのでした。最後のキャリアチェンジのタイミングとしてこれ以上ない機会ととらえ、ご縁を感じて2022年に医院を継承させていただくことになりました。これまで積み重ねてきた脳神経外科診療の経験を、地域に根ざしたかたちで活かせる医療を──と考え、開業医として新たな一歩を踏み出しました。
2023年に「もり脳神経外科クリニック」へ名称変更されたそうですね。

はい。医院の継承後、まずは地域の皆さんに親しまれてきた「古賀脳神経外科」の名をそのまま引き継ぎ、1年間診療を続けました。長年にわたり地域に根差した医院として信頼されてきた歴史を尊重し、内装なども大きく変えることなく、これまでの雰囲気や姿勢を大切にしてきました。
一方で、継承と同時に新しい取り組みにも着手しています。予約診療の導入や、クラウド型の予約システム・電子カルテの導入、キャッシュレス決済やオンラインレセプト請求、マイナ保険証への対応、画像管理システム(PACS)の導入など、診療の効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しました。
また、患者さんにより丁寧に向き合える診療環境を整えるため、ドクタークラークを採用しています。医師がカルテ入力から解放され、face to face(フェイスツーフェイス)の患者さんに寄り添った診療が可能となりました。
さらに診療機器の面でも強化を図り、2023年5月にはGE社製の高磁場1.5テスラMRI(SIGNA Creator)を導入。より高精度かつ迅速な画像診断が可能になり、診療の質も大きく向上しました。こうして新たな体制が整った節目として、2023年、「もり脳神経外科クリニック」へと医院名を変更しました。地域の皆さんに支えられてきた医院の歴史を受け継ぎながらも、より現代的で信頼されるクリニックとして、今後も進化を続けてまいります。
継承時にリフォームはされなかったとのことですが、落ち着いた雰囲気の院内ですね。

初めて訪れた際の印象は、まるで昭和のレトロな喫茶店のような趣きでした。実際に、喫茶店と勘違いして入ってこられた方もいらっしゃったほどです(笑)。
院内はダークブラウンを基調とした落ち着いた色合いで、明るすぎない、静かで安らぎのある空間になっています。こうした環境は、光や音の刺激で症状が悪化しやすい片頭痛の患者さんなどにも、安心してお待ちいただけるのではないかと感じています。
また、待ち時間を少しでも快適に過ごしていただけるよう、音響設備や環境映像などにも工夫を凝らしています。玄関横のウィンドウや院内の装飾には、ドライフラワーアーティストのwasabi.botanicalさんによる作品を取り入れ、空間全体をやわらかく穏やかな雰囲気にまとめていただきました。大がかりな改装はしていないものの、医院が歩んできた歴史やぬくもりを大切にしながら、今の診療スタイルに合った快適な空間づくりを心がけています。